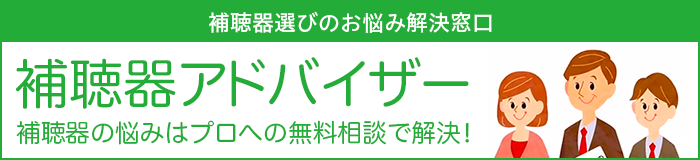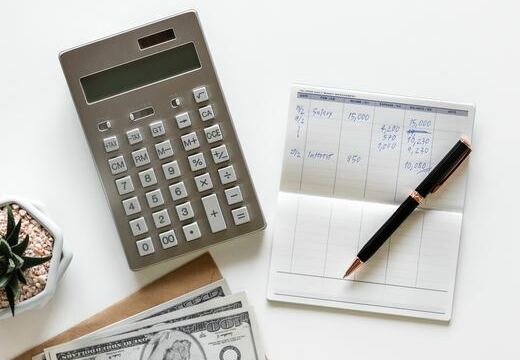私たちの毎日に欠かせない「聞こえ」を支える補聴器。その歴史はとても長く、技術の進歩とともに大きく進化してきました。
この記事では、補聴器のはじまりから最新の技術までを時系列順に解説していきます。
最古の補聴器
補聴器の役割は、音を聞きやすくすることです。 その役割だけを見ると、補聴器の歴史は紀元前にまでさかのぼることができます。
たとえば、耳の後ろに手を当てると、音が集まりやすくなるのはよく知られています。昔の人々も同じように、ほら貝や水牛の角などといった中が空洞になっている自然のものを利用して音を集める工夫をしていました。
もちろん、当時は「補聴器」という名前ではありませんでしたが、人々は日常生活の中で「音を集める道具」として役立てていたのです。こうした工夫が、補聴器のはじまりと言えるでしょう。
機械式の補聴器
時代が進むと、金属や木を使った「イヤートランペット」と呼ばれるラッパ型の補聴器が登場しました。
これは17世紀から18世紀にかけて使われるようになったものです。 イヤートランペットは、広い口の部分で音を集めて細い管を通し、耳まで届ける仕組みです。見た目は金属製のラッパのようで、作りはシンプルですが、音を集める効果はしっかりとありました。
しかし、当時はすべてが手作りだったため、とても高価なものでした。イヤートランペットを使えたのは、お金持ちや身分の高い人たちが中心だったのです。 その後、イギリス・ロンドンのフレデリック・チャールズ・レインが、イヤートランペットの改良を進めました。
レインは、小規模ながら工業生産を取り入れ、より多くの人が補聴器を使えるようにしました。
電気式補聴器
電気の力を使った補聴器が登場したのは、19世紀の終わりごろです。
1898年、アメリカのミラー・リース・ハチソンが携帯用補聴器を開発しました。これはカーボンマイクロホンを使った、初めての実用的な補聴器でした。
この補聴器には、グラハム・ベルが発明した電話の技術が応用されています。ベルが開発した「音を電気信号に変える技術」は、音をマイクで拾い、電気信号に変えてからスピーカーで再生するという仕組みで、補聴器にも活かせるものでした。
真空管アンプを使用した補聴器
1921年には真空管アンプを使った補聴器が登場し、音の増幅性能が向上しました。
真空管アンプとは、電極を入れた真空管を用いて陰極から陽極に流れる電子流を制御する装置です。電子流を制御できるので、音を増幅することができ、静かな音もはっきりと聞き取れるようになりました。
登場した当時は、真空管自体が大きく、補聴器もまだまだかさばるサイズでしたが、のちに真空管もサブミニチュア管の出現で実用的なポケット型補聴器が生産されるようになりました。
トランジスタ補聴器
1950年代になるとベル研究所が「トランジスタ」を発明し、補聴器も大きく進化します。トランジスタとは、電気を効率よくコントロールする小さな部品です。
トランジスタ補聴器は、真空管補聴器とは違い半導体の部品を用いて電力をコントロールするため、小さくて軽く、電力の消費も少ないといった特徴があります。トランジスタによって雑音が減り、より自然な音を届けられるようになったのです。
この時代から補聴器は、より日常的に使える道具として広がっていきます。
ICチップ型補聴器
1980年代に入ると、補聴器にはICチップ(集積回路)が搭載されるようになり、さらなる小型化と省電力化が進みました。
ICチップは、半導体の表面に電子回路を形成することで小さな部品の中に多くの電子回路をまとめることができる技術です。これにより、補聴器は耳の中にすっぽり収まるほどコンパクトになり、より快適に使えるようになりました。
今のデジタル補聴器もこのICチップ型をもとに作成されています。
プログラマブル補聴器
さらに1990年代には、「プログラマブル補聴器」と呼ばれる製品が登場します。
これは、使う人の聴力や使用環境に合わせて、細かな音質調整ができる補聴器です。 プログラマブル補聴器とは音声信号はアナログ回路を使い、制御はデジタル回路で行う補聴器となります。
補聴器の調整は従来ねじ回しで行っていましたが、プログラマブル補聴器にすることで専用のコンピュータを使って補聴器の設定をプログラムし、個人に最適な「聞こえ」を提供できるようになりました。
デジタルとアナログの両方の特性をもつプログラマブル補聴器はデジタル補聴器の前段階といえるでしょう。
アナログ補聴器からデジタル補聴器へ
1990年代、補聴器の技術はさらに進化します。アナログ方式からデジタル方式への転換です。
アナログ補聴器は、入ってきた音をそのまま増幅する方式でした。一方でデジタル補聴器は、音を「デジタル信号」に変えてから処理するため、不要な雑音を減らし、聞きたい音だけを強調できます。
世界初のデジタル補聴器は日本のリオン社から1991年に発売されました。その後1995年にWIDEXから世界初の耳穴型補聴器「センソ」、同年にオーティコンがフルデジタル補聴器を発売します。
チップで進化するデジタル補聴器
近年では、補聴器に使われる「チップ」がどんどん高性能になり、AI(人工知能)まで搭載されるようになりました。これにより、周囲の環境音を自動で判断し、会話に集中できるように調整する機能が備わっています。
たとえば、静かな場所では自然な音質を、にぎやかな場所では声を強調してくれるのです。また、スマートフォンと連携し、アプリで音量調整や設定変更が簡単にできるようになっています。
補聴器は「音を大きくする」だけでなく、「快適に聞く」ための高度な機械へと進化しているのです。
日本での補聴器の歴史
日本では江戸時代、蘭学者の司馬江漢が1813年、オランダ人の指導のもとで蘭学書「ボイス」に掲載されていた図を参考に、ラッパ型の耳当て補聴器を開発しました。司馬江漢はこの補聴器を「耳鏡(じきょう)」と名付けています。
1930年にはカーボンマイクロホンを用いた補聴器が国内で作られました。本格的に補聴器が市販されるようになったのは、戦後まもない1948年ごろのことです。
その後、1950年には身体障害者福祉法が施行され、補聴器が補装具として指定されます。1955年から1956年にかけてトランジスタ補聴器が発売されるとともに、補聴器の普及が本格的に進みました。
おわりに
補聴器の歴史をたどると、人々が「聞こえ」をあきらめず、技術を進化させてきた努力がよくわかります。
補聴器の歴史を知ることで、そのありがたみを感じていただけたら嬉しいです。
当記事があなたの参考になれば幸いです。